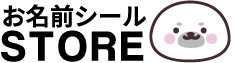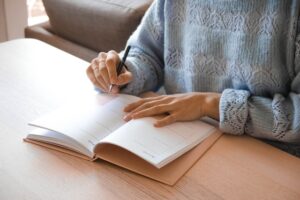小学校入学の準備を進める中で、意外と悩むのが「上履き選び」。ランドセルや学習机などに比べると目立たないアイテムですが、毎日使うものだからこそ慎重に選ぶ必要があります。
上履きは、学校の教室や廊下などで履くための靴です。子どもは長時間履き続けることになるため、足に合わないものを選んでしまうと、歩きにくさや疲れやすさにつながるだけでなく、足の成長に影響を与えることもあります。「大きめを買えば長く使える」と思いがちかもしれませんが、実は上履きは子どもの足の発達に大きな影響を与える重要なアイテムです。
本コラムでは、上履きを選ぶ際に気をつけたいポイントを詳しく解説します。サイズの選び方や種類ごとの特徴、足の成長を考慮した適切な選択肢、さらにはお手入れ方法まで紹介します。お子さんが快適に学校生活を送れるよう、ぜひ参考にしてみてください。
小学校の上履きに求められる条件

小学校で使用する上履きは、ただ履ければいいというものではありません。毎日長時間履くものだからこそ、子どもの足に優しく、動きやすいものを選ぶことが大切です。では、具体的にどのような条件を満たしていると良いのでしょうか?
学校の指定があるか確認する
まず、上履きを購入する前に、学校から指定があるかを確認しましょう。学校によっては、「白いバレエシューズ型」「ゴム底で白のみ」など、色や形に決まりがある場合があります。また、キャラクターものが禁止されていることもあるため、事前に入学説明会や学校の配布資料をチェックすることが重要です。
通気性が良いものを選ぶ
子どもは新陳代謝が活発で、足にも汗をかきやすいです。通気性の悪い上履きを履いていると、ムレやニオイの原因になり、不快感につながります。特に、ビニール製のものよりも、メッシュ素材や布製のものが適しています。また、インソール(中敷き)が取り外せるタイプなら、定期的に洗うことで清潔に保てます。
脱ぎ履きしやすいデザイン
小学校では、上履きを履いたり脱いだりする場面が多くあります。たとえば、体育の授業で運動靴に履き替えるときや、掃除の時間に床を拭くときなどです。履き口が広く、子どもが自分で簡単に脱ぎ履きできるものを選ぶと、学校生活がスムーズになります。特に、マジックテープタイプの上履きは、フィット感を調整できるうえに脱ぎ履きしやすいのでおすすめです。
足にフィットするサイズ感
大きすぎる上履きは、歩くたびにかかとが浮いて脱げやすくなり、転びやすくなります。一方で、小さすぎると窮屈で足の成長を妨げる原因に。適切なサイズの目安として、つま先に5mm〜10mmほど余裕があり、かかとがしっかりフィットしているものを選びましょう。試し履きをして、かかとが浮かずにしっかり固定されるかをチェックすると安心です。
滑りにくいソール(靴底)
学校の廊下や体育館は、滑りやすいことがあります。特に、雨の日などは廊下が濡れていることもあるため、滑りにくいゴム底のものを選ぶと安心です。かかと部分に適度なクッション性があると、長時間履いても疲れにくくなります。
サイズ選びのポイント
上履きを選ぶ際に特に重要なのが「サイズ選び」です。サイズが合わない上履きを履き続けると、歩きにくさや疲れやすさだけでなく、足の成長にも悪影響を与える可能性があります。「大きめを買って長く履かせよう」と考える方も多いですが、実はこれは間違った選び方です。ここでは、子どもにぴったりの上履きを選ぶためのポイントを解説します。
つま先に5mm〜10mmの余裕を持たせる
適切なサイズの目安は、つま先に5mm〜10mmほどの余裕があることです。これ以上大きいと足が中で動いてしまい、不安定な歩行につながります。逆に、小さすぎると指が圧迫されてしまい、足の成長を妨げる原因になります。
かかとがしっかりフィットするものを選ぶ
上履きを履いたときに、かかと部分が浮かずにしっかり固定されていることが大切です。かかとが緩いと、歩くたびにズレてしまい、転びやすくなります。試し履きをするときは、実際に歩いてみてかかとが浮かないか確認しましょう。
幅が合っているかチェックする
足の幅は個人差が大きく、同じサイズでも「細身のもの」「幅広のもの」があります。足の幅が広めのお子さんには、幅広タイプの上履きを選ぶと快適に履くことができます。履いたときに足が圧迫されていないか、また逆にブカブカすぎないかを確認しましょう。
靴下を履いた状態で試し履きをする
学校では基本的に靴下を履いたまま上履きを履くため、試し履きをする際も普段履いている靴下を履いた状態でサイズを確認しましょう。特に冬場は厚手の靴下を履くことが多いため、季節ごとの履き心地も考慮すると良いです。
1年に数回サイズチェックをする
子どもの足は成長が早く、半年〜1年で0.5cm〜1cmほど大きくなることもあります。新学期前や長期休みの前などにサイズをチェックし、上履きが小さくなっていないか確認しましょう。特に「最近、上履きを履くのを嫌がる」「歩き方がぎこちない」と感じたときは、サイズが合っていない可能性があるため、買い替えを検討しましょう。
上履きの種類と選び方
上履きにはさまざまな種類があり、それぞれ特徴や履き心地が異なります。学校の指定がない場合は、子どもの足に合ったものを選ぶことが大切です。ここでは、代表的な上履きの種類と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
バレエシューズ型(スリッポンタイプ)
| |
特徴:
- つま先が丸く、甲の部分にゴムがついているシンプルなデザイン
- 軽量で、履きやすく脱ぎやすい
メリット:
- シンプルなデザインで、多くの学校で使いやすい
- 軽くて動きやすい
- 価格が比較的安い
デメリット:
- かかとのフィット感が弱く、脱げやすいことがある
- 甲の部分のゴムがきついと、締め付けを感じる子もいる
→ こんな子におすすめ: 足の幅が細めで、軽い靴を好む子
ベルト付き(マジックテープタイプ)
| |
特徴:
- 甲の部分にマジックテープのベルトがついており、フィット感を調整できる
メリット:
- 足にしっかりフィットし、脱げにくい
- マジックテープで調整できるので、成長に合わせやすい
- 履き口が広いため、脱ぎ履きがしやすい
デメリット:
- バレエシューズ型に比べるとやや重め
- マジックテープが劣化すると粘着力が弱くなる
→ こんな子におすすめ: 足の幅が広めで、しっかりと固定できる靴を好む子
メッシュタイプ(通気性重視)
| |
特徴:
- アッパー部分にメッシュ素材を使用し、通気性を高めたタイプ
メリット:
- 通気性が良く、ムレにくい
- ニオイがこもりにくく、快適な履き心地
- 軽量で、動きやすい
デメリット:
- 一般的な布製の上履きよりも価格が高め
- 学校によっては指定のデザインに合わない場合がある
→ こんな子におすすめ: 足が蒸れやすく、汗をかきやすい子
体育館シューズタイプ(クッション性重視)
| |
特徴:
- ソール(靴底)が厚めで、クッション性が高いタイプ
メリット:
- 長時間履いても疲れにくい
- クッション性があり、足への負担を軽減できる
- 滑りにくいゴム底で、安全性が高い
デメリット:
- 他のタイプに比べて重め
- 価格がやや高め
→ こんな子におすすめ: 活発に動くことが多く、足への負担を減らしたい子
選び方のポイント
- 学校の指定を確認する → まずは指定の有無をチェック!
- 子どもの足の形に合ったものを選ぶ → 足幅や甲の高さに合わせた上履きを選ぶ
- 試し履きをしてフィット感を確認する → かかとが浮かず、つま先に適度な余裕があるかチェック
上履きは毎日使うものだからこそ、子どもが快適に過ごせるものを選ぶことが大切です。次の章では、上履きを長持ちさせるためのお手入れ方法について紹介します。
足の成長と上履きの関係
子どもの足は成長が早く、特に小学校低学年の時期は半年から1年で0.5cm〜1cmも大きくなることがあります。そのため、成長に合わせた上履きを選ばないと、足に負担がかかり、健康な発育を妨げる可能性があります。ここでは、子どもの足の成長と上履きの関係について詳しく解説します。
子どもの足はどう成長する?
子どもの足は大人の足とは異なり、骨がまだ柔らかく、発育の途中にあります。そのため、足に合わない靴を履き続けると、骨や筋肉の発達に影響を与えることがあります。
- 0〜3歳:足の骨はまだ軟骨が多く、柔らかい状態
- 4〜6歳:足のアーチ(土踏まず)が形成され始める
- 7〜12歳:骨格がしっかりしてきて、大人の足に近づいていく
特に小学校低学年の時期は、足の形がどんどん変化するため、定期的に上履きのサイズを見直すことが大切です。
サイズが合わない上履きが与える影響
サイズが合わない上履きを履き続けると、次のような問題が起こる可能性があります。
小さい上履きの影響
- 足の指が圧迫され、成長の妨げになる
- 血行が悪くなり、足の冷えや疲れやすさにつながる
- 足の変形(外反母趾や扁平足)の原因になる
大きすぎる上履きの影響
- かかとが浮いて歩きづらく、転びやすくなる
- 足の指で無理に踏ん張るため、疲れやすくなる
- 正しい歩き方が身につかず、姿勢の悪化につながる
足の成長に合わせた上履きの選び方
足の成長をサポートするためには、以下のポイントを意識して上履きを選びましょう。
✔ 定期的にサイズチェックをする
- 目安として、半年に1回は足のサイズを測り、上履きが合っているか確認しましょう。
- 子ども自身が「キツイ」「痛い」と言わなくても、小さくなっていることがあるので注意が必要です。
✔ クッション性があり、足に優しいものを選ぶ
- 床が硬い学校の教室では、クッション性のある靴底の上履きを選ぶと、足への負担を軽減できます。
- 中敷きを入れ替えられるタイプもおすすめです。
✔ 靴下を履いた状態でフィットするか確認する
- 学校では靴下を履いたまま上履きを使うため、靴下を履いた状態で試し履きをしましょう。
- つま先に5mm〜10mmの余裕があることが理想的です。
✔ かかとがしっかり固定されるものを選ぶ
- かかとが浮かず、しっかりフィットしているものを選びましょう。
- マジックテープ付きのタイプは調整がしやすくおすすめです。
子どもの足は日々成長しています。その成長を妨げないよう、定期的なサイズチェックと適切な上履き選びを心がけましょう。次の章では、上履きを長持ちさせるためのお手入れ方法について解説します。
上履きの手入れ方法
子どもが毎日使う上履きは、汚れや臭いがつきやすく、衛生面でも気になるもの。定期的なお手入れをすることで清潔さを保ち、長持ちさせることができます。ここでは、上履きの正しい洗い方や乾かし方について詳しく解説します。
上履きを洗う頻度は?
理想的な洗う頻度は「週に1回」。汚れをため込まず、こまめに洗うことでカビや臭いの発生を防ぎます。
洗う前の準備
【準備するもの】
| |
- 洗剤(中性洗剤やウタマロ石鹸など)
- 古い歯ブラシや靴用ブラシ
- バケツまたは洗面器
- 重曹や酸素系漂白剤(臭いや黄ばみが気になる場合)
基本の洗い方
| |
まずは泥汚れを落とす
乾いた状態で靴底や側面についた泥汚れを、ブラシで落とします。ぬるま湯に漬ける
40℃程度のぬるま湯に上履きを浸け、汚れを浮かせます。洗剤でしっかりこすり洗い
靴用ブラシや古い歯ブラシを使って、ゴム部分や布の隙間まで丁寧にこすります。
汚れが落ちにくい場合はウタマロ石鹸がおすすめ!しっかりすすぐ
洗剤が残ると臭いや黄ばみの原因になるため、流水でしっかりすすぎます。タオルで水気を取る
乾いたタオルで水分を拭き取り、型崩れを防ぎます。
頑固な汚れや臭いには「つけ置き洗い」
| |
黄ばみや頑固な汚れには、重曹や酸素系漂白剤を使った「つけ置き洗い」がおすすめ!
【つけ置き方法】
- バケツにぬるま湯を入れ、重曹または酸素系漂白剤を溶かす
- 上履きを1〜2時間ほど浸ける
- その後、通常通り洗剤でこすり洗いする
乾かし方のポイント
× 直射日光で乾かすと、ゴム部分が劣化して黄ばみの原因に!
✓風通しの良い日陰で干すのがベスト
✓ 中に新聞紙を詰めると、水分を吸収しながら型崩れも防げる
上履きを清潔に保つコツ
- 防水スプレーで汚れを防ぐ
- 使わない日は除湿剤や乾燥剤を入れておく
- 消臭効果のある重曹パウダーを靴の中に入れる
上履きを洗う時の簡単裏ワザ!
| |
★上履き専用の洗濯ネットに入れて、洗濯機で洗う方法も◎
※ ただし、洗濯機で洗う場合は「弱水流モード」に設定し、型崩れ防止のため必ずネットに入れましょう。
上履きの手入れを習慣化することで、清潔に保ち、長く快適に使うことができます。子ども自身が「自分で洗う習慣」を身につけることも、成長の一歩になりますよ!
まとめ
小学校生活に欠かせない上履きは、子どもの足の成長や健康に大きく影響を与える重要なアイテムです。正しい上履きを選ぶことで、足のトラブルを防ぎ、快適な学校生活をサポートすることができます。
上履き選びでは、「通気性」「フィット感」「安全性」などの条件を意識し、子どもの足に合ったサイズを選ぶことが大切です。また、成長に合わせて定期的にサイズを見直し、足の健康を守ることも忘れずに。
さらに、週に1回の手入れや正しい乾かし方を習慣化することで、清潔で快適な状態をキープすることができます。子ども自身にお手入れの習慣を身につけさせることも、学びの一環としておすすめです。
これから小学校入学を迎えるご家庭の方は、ぜひこの記事を参考に、子どもにぴったりの上履きを選び、楽しい学校生活をサポートしてあげてくださいね。